― 損益通算/枠復活/配当の非課税をやさしく整理 ―
TL;DR(まずは3行で)
- 損益通算・損失繰越は不可。NISAの損は課税口座の利益と相殺できない。
- 年間投資枠は繰越不可。売却で枠は当年復活しない(翌年以降に簿価分だけ戻る)。
- 国内上場の配当・分配金は株式数比例配分方式で受け取る設定にして非課税を確実化。
1. 基本ルール(ここだけは覚える)
1-1. 年間枠と生涯枠
- 年間投資枠:つみたて120万円+成長240万円=最大360万円/年。
- 繰越不可:使い残しは翌年に持ち越せない。
- 生涯非課税保有限度額:合計1,800万円(うち成長は1,200万円)。無期限保有。
1-2. 売却と“枠復活”
- 当年は戻らない。
- 翌年以降に、売った商品の簿価(取得金額)分だけ復活。
1-3. 損益の取り扱い
- 損益通算×/損失繰越×(課税口座の利益と相殺不可)。
- 配当・分配金:国内上場分は受取方式の設定で非課税に。海外分は現地の源泉税が残る。
2. よくある誤解Q&A(各項目にミニ具体例つき)
Q1. 「NISAで損が出た。課税口座の利益と相殺できる?」
A:できません。
例:NISAで**−10万円**、課税口座で**+8万円**の利益
→ 相殺不可。課税口座の+8万円には通常どおり課税。
Q2. 「年間枠、今年は50万円しか使わなかった。来年は360+50=410万円使える?」
A:使えません。
例:今年50万円使用 → 残り310万円は消滅。来年の上限はまた360万円。
Q3. 「100万円で買った投信を120万円で売った。枠は120万円戻る?」
A:戻りません。
例:買値(簿価)100万円 → 翌年以降に100万円だけ復活(20万円の利益は非課税のままあなたの利益)。
Q4. 「NISAで配当は全部非課税なんでしょ?」
A:設定次第で課税されることがあります。
国内上場の配当・分配金は、受取方式を“株式数比例配分方式”にすることで非課税。
例:銀行口座受取のままだと課税扱い→要変更。
設定手順(一般的な流れ)
証券会社マイページ → 口座管理 → 配当金受取方式 → 株式数比例配分方式を選択
※権利確定日前に設定。1回の設定で他口座も原則比例配分方式になります。
Q5. 「米国ETFの分配金も完全に非課税?」
A:日本では非課税ですが、米国での源泉税(条約税率10%など)はかかります。
例:1万円の分配金 → 米国で1,000円源泉 → 日本では非課税で9,000円受取。
NISAは日本で非課税のため、外国税額控除は使えません。
Q6. 「成長投資枠ならどんなETF・投信でも買える?」
A:一部対象外があります。
例:毎月分配型、高レバレッジ型、信託期間が短い投信などは除外のことがある→買付前に“対象商品”か確認。
Q7. 「同じ年に別の証券会社でもNISAを使いたい」
A:同一年は1人1口座・同一金融機関のみ。
例:A社でNISAを使い始めたら、同じ年にB社で新規NISAは不可**(年単位で変更は可)。
3. NG行動チェック
- 配当受取方式を未設定 → 国内上場の配当・分配金が課税に。
- 年初に枠を全部使い切り → 急落時の好機に弾切れ。
- 高コスト/毎月分配を“コア”に採用 → 複利を削る。
- レバレッジETFやテーマ特化を積立の中心に → 価格変動が大きく長期の土台に不向き。
- “売ればすぐ枠復活”と思い込み → 復活は翌年以降、しかも簿価のみ。
4. 用語ミニ辞典
- 年間投資枠:その年に新たに買える上限。つみたて120万+成長240万=360万まで。繰越なし。
- 生涯非課税保有限度額:生涯で保有できる“買値(簿価)”の合計上限。1,800万(成長は1,200万まで)。無期限。
- 簿価(取得金額):買ったときの購入代金。値上がり・値下がり後の時価ではない。
- 株式数比例配分方式:配当等を証券口座で受け取る方法。NISAの非課税を適用する鍵。
- 損益通算:A口座の損とB口座の利益を相殺すること。NISAの損は対象外。
- 外国税額控除:海外で源泉された税金を日本の税金から差し引く制度。NISAの配当は日本で非課税なので基本使えない。
5. すぐできるセルフ点検
- 今年の年間枠の残りはいくら?(繰越不可を意識)
- 配当受取方式は株式数比例配分方式にした?
- 予定している売却は翌年以降の枠復活まで見越して計画?
- 買おうとしている商品は対象外じゃない?
- つみたて=土台/成長=伸びしろの役割分担は明確?
6. 関連記事
迷ったらまず全体像から。関連記事は見出しの通りに読み進めると迷いません👇
- 【連載①】新NISAの設計と“枠復活”の仕組み
→ 年間枠・生涯枠・簿価復活を図で理解(/nisa-framework/) - 【連載②】つみたて投資枠の選び方
→ 指数・コスト・リバランスの基礎(/nisa-tsumitate/) - 【連載③】成長投資枠の攻め方
→ ETFをコアに、個別株はサテライト(/nisa-growth/) - 【連載④】口座の作り方・金融機関の選び方
→ 受取方式の設定と乗り換え手順(/nisa-account/)
7. まとめ
- “非課税の器”=NISA。**損益通算×/繰越×/当年復活×**を押さえれば怖くない。
- 配当の非課税は受取方式の設定が鍵。
- 売却→翌年以降に簿価分復活を味方につけ、計画的に枠を使うのがコツ。
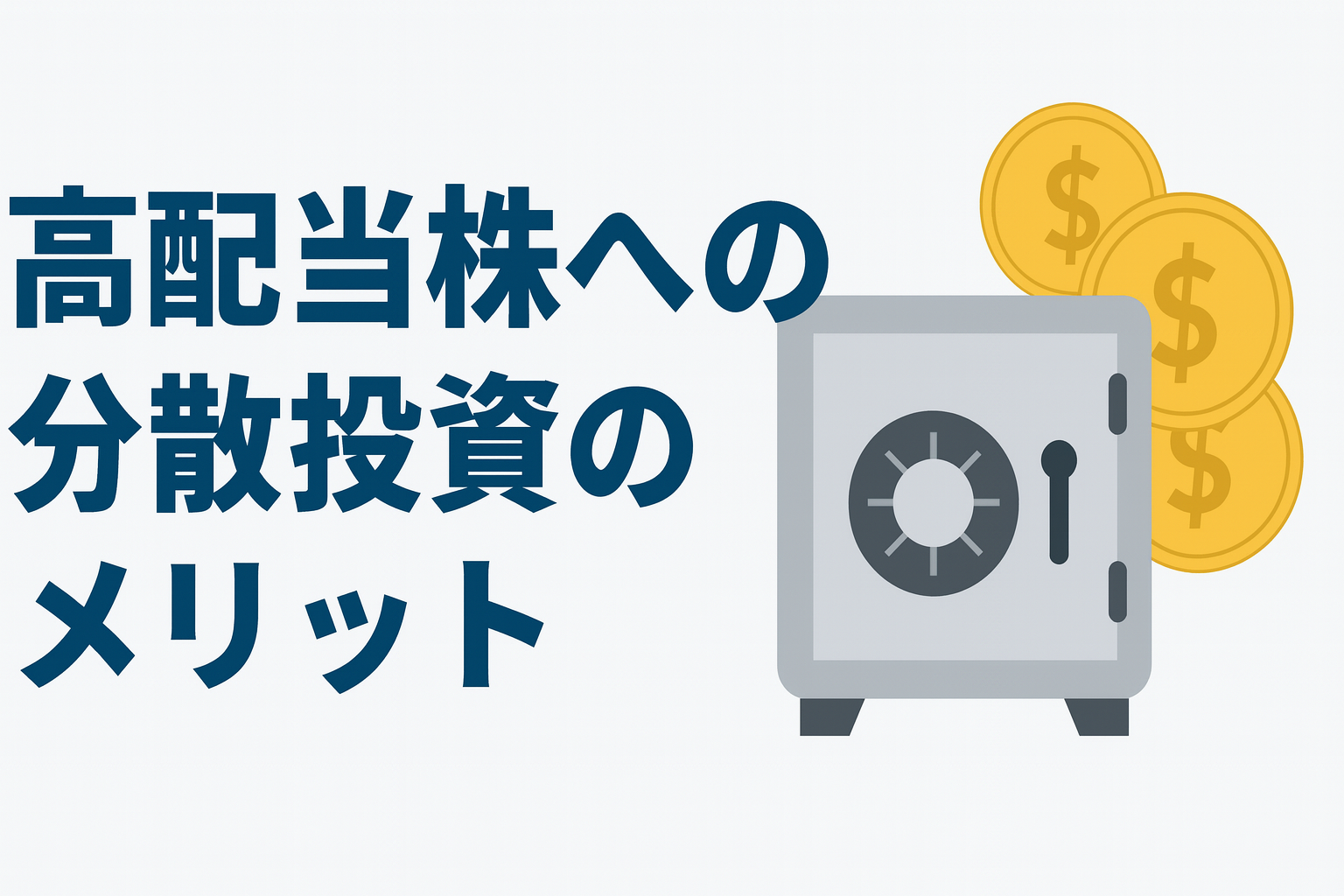
コメント