先に3行まとめ
- NISAは同一年・同一金融機関で1人1口座。つみたて投資枠と成長投資枠を別の金融機関に分けて使うことは不可。年単位で乗り換えは可能です。
- 口座開設は、金融機関でNISA口座の申込+マイナンバー等の本人確認が必須。必要書類は国税庁の案内が一次情報です。
- 金融機関選びは「コスト・取扱商品・アプリ/積立機能」の3軸でOK。つみたて枠や成長枠の対象商品リストは公式で公開されています。
1. まず決めること:どの金融機関で“両方の枠”を使うか
- 同一年は1人1口座・同一金融機関のみ(つみたて枠と成長枠を別々にはできません)。
- 金融機関は年単位で変更可能(乗り換え自体は制度上OK)。
迷ったら:最初は“アプリが使いやすく、つみたて設定が柔軟”なネット証券が無難。あとで年単位で乗り換えもできます。
2. NISA口座の開設フロー(実務ベース)
- 金融機関を選ぶ(後述の3軸チェックで比較)
- 証券総合口座+NISA口座の申込
- 本人確認(マイナンバーと本人確認書類の提出)
- (金融機関側で重複申請がないかの確認)
- 開設後の初期設定
- 自動積立の設定(つみたて投資枠)
- 配当・分配金の受取方式を株式数比例配分方式へ(国内上場の配当等を非課税で受け取るため)
ミニ解説:株式数比例配分方式
上場株/ETF/REITの配当等を証券口座で受け取る方式。NISAの非課税を適用するには原則この設定が必要です。権利確定“前”に設定しましょう。
3. 金融機関選びの3軸チェック
3-1. コスト(手数料と運用コスト)
- 売買手数料の体系(国内株・海外株・ETF)
- 投信の信託報酬・実質コスト(つみたて枠は低コスト前提の商品が中心)
3-2. 取扱商品の幅
- つみたて投資枠:対象の投資信託や一部ETFの品揃え(公式リストで下見)。
- 成長投資枠:国内株・ETF・REITに加え、NISAで買える投信の範囲(投信協会の一覧参照)。
3-3. アプリ/積立機能・運用サポート
- 積立の柔軟性(日付・増額・ボーナス設定、カード/口座引落など)
- 画面の見やすさ・通知機能(積立実行/失敗通知、目標達成度)
- 検索/比較(指数・コスト・純資産・リスクのフィルタ)
4. 乗り換え(金融機関変更)のやり方と注意点
手順(制度のルールに沿って)
- 現在の金融機関に**「金融商品取引業者等変更届出書」**を提出 → **「勘定廃止通知書」**を受け取る。
- 新しい金融機関へ**「非課税口座開設届出書」+その勘定廃止通知書**を提出。
- 提出時期:変更したい年の前年10/1〜当年9/30に手続書類を提出する必要があります。
大事な制約
- その年に旧口座で買付があると、その年分は変更不可(翌年以降) 。
- 旧口座のNISA資産は、新口座へ“非課税のまま移管不可”。売却しない限り、旧口座で非課税のまま保有継続になります。
使い分けのコツ
長期保有のNISA資産はそのまま残し、新規買付を新口座で行う運用でもOK(非課税は維持)。ただし管理が二拠点になる点は要留意。
5. 申し込み前の“準備チェックリスト”
- ✅ 本人確認書類(運転免許証など)+マイナンバー(個人番号カード/通知カード+本人確認書類/個人番号付き住民票)を用意。
- ✅ 入金ルート(銀行口座の登録)
- ✅ つみたて設計(毎月いくら・コア/サテライトの比率)
- ✅ 配当受取方式=株式数比例配分方式の設定。
- ✅ 二段階認証や通知設定(セキュリティ/積立失敗アラート)
6. つみたて・成長の“土台づくり”テンプレ(最初の1週間でやること)
- 口座開設申込→ 本人確認書類とマイナンバーアップロード。
- 自動入金/カード引落を登録(積立の止まりを防ぐ導線づくり)
- つみたて投資枠:全世界株などコア投信を自動積立に設定(毎月/隔週)
- 成長投資枠:コアETF(国内/全世界)をお気に入り登録→分散ルールと金額だけ決める
- 株式数比例配分方式を設定(国内配当の非課税を逃さない)
7. 参考リンク(一次情報)
- 金融庁 NISA Q&A:1人1口座、金融機関変更、枠の基本。
- 金融庁 スライド資料(2024以降):新制度の全体像・ルール要点。
- 国税庁:NISA口座の手続(必要書類=マイナンバー等)。
- 金融庁:対象商品一覧(つみたて枠/投信協会リンク)。
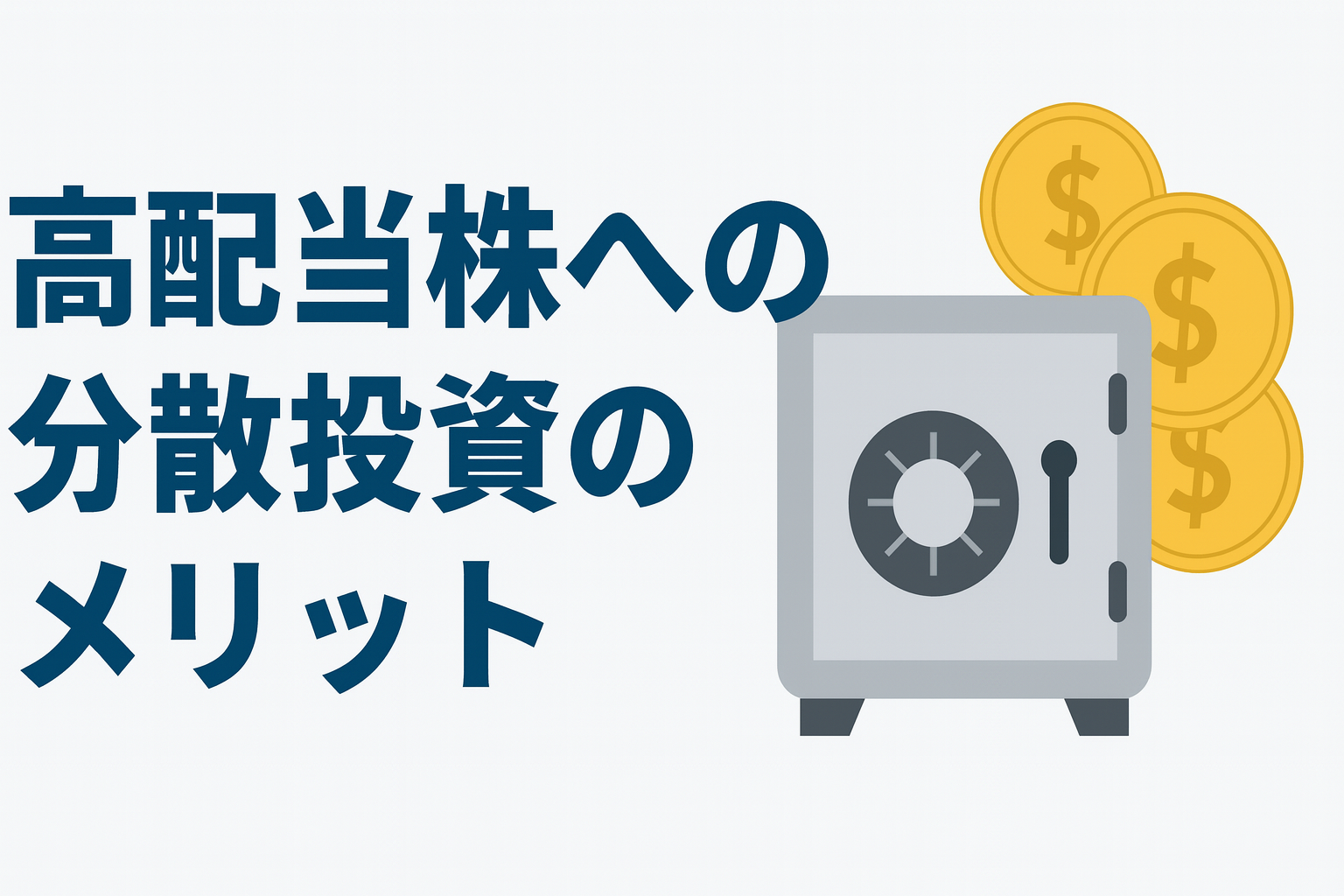
コメント