― “非課税のNISA” と “所得控除のiDeCo” をどう使い分ける? ―
TL;DR(3行で要点)
- NISAはいつでも引き出せる“非課税の器”。一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに掛金が“全額所得控除”。
- 税率が高い人ほどiDeCoの節税が強力(掛金×〔所得税率+住民税率〕)。ただし流動性はゼロに近い。
- 併用の基本順は①生活防衛資金 → ②NISA(つみたて枠)→ ③勤務先DC(あれば)→ ④iDeCo → ⑤NISA(成長枠)。理由は流動性と恒久的非課税を先に確保するため。
1. まず“制度の芯”だけ押さえる
NISA(新NISA)
- 利益・配当が非課税/無期限、生涯非課税保有限度額1,800万円(成長投資枠は1,200万円)。損益通算や損失繰越は不可。
- 引き出し自由(売却はいつでも可)。=流動性が高い。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 掛金が“全額所得控除”(小規模企業共済等掛金控除)、運用益も非課税、受取時も控除(退職所得控除/公的年金等控除)。
- 原則60歳まで引き出せない(加入年数により受取開始年齢が繰下がる/上限は75歳までに請求)。
用語ミニ解説
所得控除:課税所得を減らす仕組み。控除額=「iDeCo掛金の年間合計」。
小規模企業共済等掛金控除:iDeCoの掛金に使う控除枠の名前。
2. “どっちがトク?”は税率×流動性で決める
節税の効き方(超シンプル式)
- 年間の節税額 ≒ 掛金合計 ×(所得税率+住民税10%)。公式サイトのシミュレーターも同じロジックで試算できます。
具体例1(会社員・課税所得330〜695万円帯=所得税20%想定)
- iDeCoを月2.3万円(上限)=年27.6万円
- 節税額 ≒ 27.6万 ×(20%+10%)= 約8.28万円/年(復興税等は簡略化)。
具体例2(公務員・会社員で企業年金あり:上限月2万円**)**
- 年24万円 ×(20%+10%)= 約7.2万円/年。
※住民税は一律10%。所得税率は課税所得で変動(5〜45%)。シミュレーターで個別に要確認。
3. 上限・手数料・年齢の“ルール”早見
掛金上限(主な区分)
- 第1号(自営業等):6.8万円/月(国民年金基金や付加保険料と合算上限)。
- 第2号(会社員)企業年金なし:2.3万円/月。
- 第2号(会社員)企業年金あり:2.0万円/月(企業型DCやDBの額に応じて縮む:5.5万円−事業主掛金−DB相当額)。
- 第3号(専業主婦/主夫等):2.3万円/月。
(いずれも最低5,000円/月・1,000円刻みで設定可)
手数料(代表例)
- 初回:2,829円(連合会に支払う新規加入/移換手数料)。
- 毎月:171円=連合会105円+信託銀行66円(運営管理機関手数料0円の会社もあり)。
受取開始年齢
- 原則60歳以降(加入期間10年以上で60歳、短いほど61〜65歳に繰下げ)/請求は75歳まで。
注意:企業型DCのマッチング拠出や他制度の加入状況によって、iDeCoの上限が0〜2万円へ圧縮されることがあります(式:5.5万円−事業主掛金−DB相当額)。勤務先の人事へ確認を。
4. 実務でのおすすめ併用順(理由つき)
- 生活防衛資金(6〜12か月)
→ まず“引き出せる現金”で土台を。 - NISA|つみたて投資枠
→ 無期限・非課税でコア資産形成。必要なら売却も可。 - 勤務先の企業型DC(マッチングや拠出が厚い場合)
→ 事業主拠出やマッチングの“実質上乗せ”を優先。 - iDeCo
→ 税率が高い人ほど強力。ただし60歳まで拘束なので、家計の余力が前提。 - NISA|成長投資枠
→ コア完成後の“伸びしろ”。売却・入替の自由度が高い。
5. ケース別ミニプラン(月の投資枠イメージ)
A|20代会社員(独身・税率10%帯)
- NISAつみたて:2万円/成長:0.5万円(慣れるまで控えめ)
- iDeCo:0〜5千円(控除は小さい。まずは流動性を優先)
B|30代共働き(税率20%帯)
- NISAつみたて:3万円/成長:1万円
- iDeCo:夫2万円・妻2万円(合計約14.4万円/年の節税効果の目安)
C|40代会社員・企業年金あり(税率23%帯)
- NISAつみたて:3万円
- iDeCo:上限2万円(約7〜8万円/年の節税)+ボーナスでNISA成長。
さらに深掘り:
つみたての中身は全世界株の低コスト投信を土台に(連載②)。成長枠の使い方はETF+必要最小限の個別(連載③)。
→ 【連載②】つみたて投資枠の選び方(/nisa-tsumitate/)|【連載③】成長投資枠の攻め方(/nisa-growth/)
6. よくある誤解と落とし穴(例で理解)
- Q.「iDeCoはいつでも辞めて全額引き出せる?」
A. 不可。原則60歳まで引き出せない。掛金は一時停止できても、資金は拘束される。 - Q.「会社のDCに入ってても、iDeCoは満額いける?」
A. 条件あり。上限2万円が最大で、**式(5.5万−事業主掛金−DB相当額)**で縮むことも。 - Q.「iDeCoは手数料がゼロ?」
A. 初回2,829円/毎月171円(運営管理手数料0円の会社を選んでも、連合会105円+信託66円はかかる)。 - Q.「NISAの方が節税は弱い?」
A. 性質が違う。NISAは利益・配当が恒久非課税で、いつでも売れる。iDeCoは今の税負担を減らすが、流動性ゼロ。
7. 今日のチェックリスト(60秒)
- 税率(今の課税所得帯)を把握した?
- 生活防衛資金は6〜12か月分ある?
- NISAつみたて枠は“自動積立”で埋めている?(無期限・非課税)
- iDeCoの上限(あなたの区分)は?計算式は5.5万−事業主−DBの確認を。
- 手数料(2,829円+月171円)と引出不可でも続けられる?
8. 内部リンク(強調版:次に読む)
NISA×iDeCoの“土台→伸びしろ”設計はこの順で読むと迷いません👇
- 【連載②】つみたて投資枠の選び方(指数・コスト・リバランス)→ /nisa-tsumitate/
- 【連載③】成長投資枠の攻め方(ETFと個別のさじ加減)→ /nisa-growth/
- 【連載⑤】誤解とNG行動Q&A(枠復活・配当非課税の設定)→ /nisa-faq-ng/
- 【連載④】口座の作り方(受取方式や乗り換えルール)→ /nisa-account/
9. まとめ
- 今の可処分所得を増やす目的なら iDeCo(高税率ほど有利)。
- 将来の自由度と売却機会を残すなら NISA(無期限非課税&流動性)。
- 結論:家計の“守り”(現金)→“土台”(NISAつみたて)→“節税の厚み”(iDeCo)→“伸びしろ”(NISA成長)の順で、無理なく両立させよう。
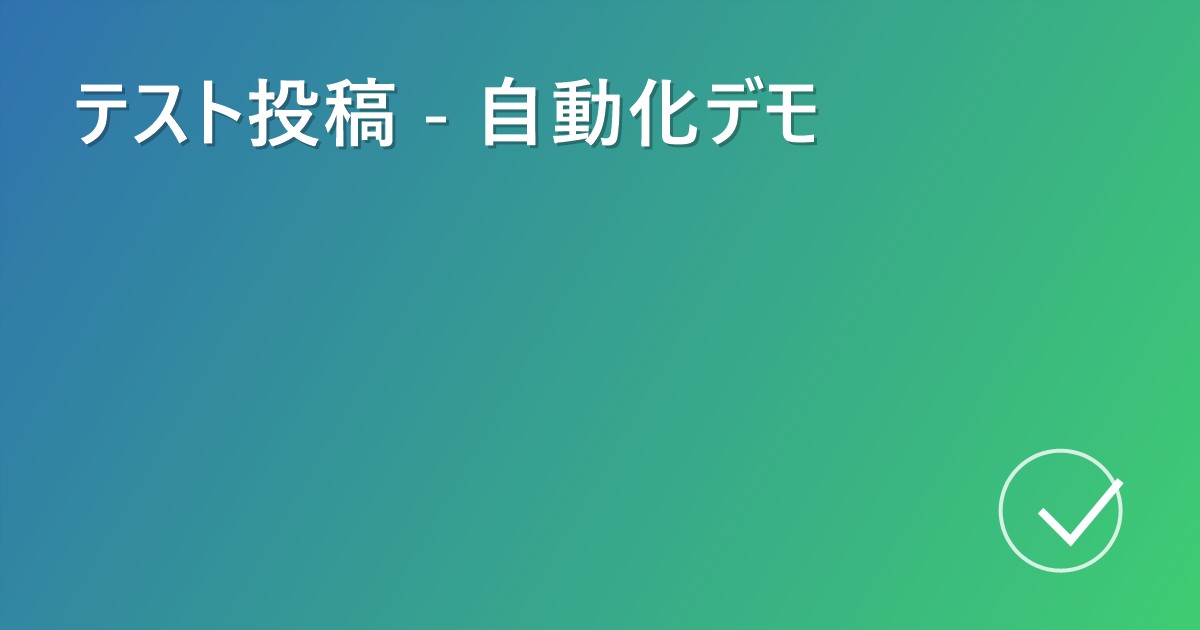
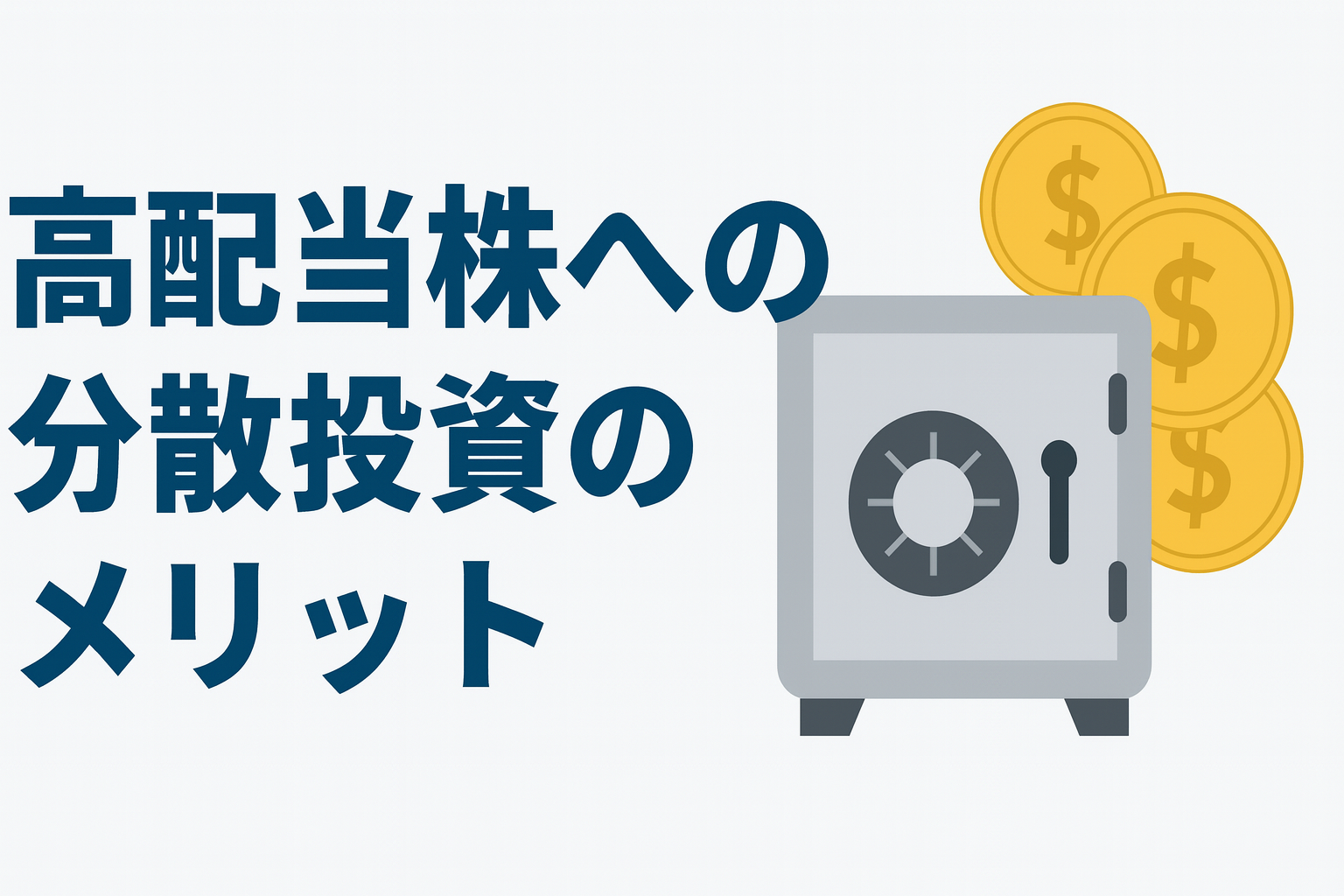
コメント